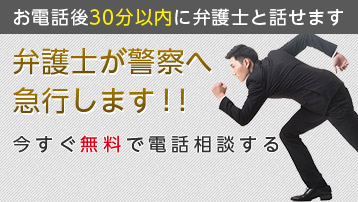示談したのに起訴された!? 不起訴・前科を防ぐためには
- その他
- 示談したのに起訴

令和3年8月、山梨県内の公立高校の教諭が女子生徒のスカート内を盗撮した事件の判決が、甲府地裁都留支部で言い渡されました。被告人の男は、校舎内で4人の女子生徒に対し盗撮行為をはたらいた罪に問われていましたが、一部の生徒との示談成立が評価されたことで、懲役1年の求刑に対して執行猶予3年が付されています。
この事例のように、たとえ有罪となった場合でも被害者との示談が成立すれば執行猶予など、比較的有利な処分が下される可能性があります。しかし一方で、たとえ示談が成立していても起訴されて有罪になってしまう危険もあるのです。
本コラムでは、刑事事件における示談の意味や効果、示談交渉に失敗してしまった場合におきること、不起訴を得るために押さえておくべきポイントを、ベリーベスト法律事務所 甲府オフィスの弁護士が解説します。
1、刑事事件における示談
示談とは、本来は加害者と被害者の間で問題解決を図る“民事的な性格”をもつものです。
ただし、被害者が存在する刑事事件においては、示談が成立しているか否かが事件の処分に大きな影響を与えます。まずは示談の意味や効果を確認していきましょう。
-
(1)そもそも示談とは?
示談とは、法的トラブルの当事者同士が話し合って問題を解決することを指します。当事者となるのは個人はもちろん、法人も含みます。
たとえば不注意で貴重品を壊してしまった、交通事故で相手の車を損傷させたといったトラブルの解決に用いられます。
問題の解決に向けて話し合いのテーブルを設けることを示談交渉と呼び、条件にお互いが合意すれば、示談成立となります。 -
(2)刑事事件における示談の効果
刑事事件における示談とは、加害者と被害者が裁判外で話し合いをして解決することを意味します。
加害者が慰謝料などの損害賠償金を含めた示談金の支払いを約束・履行することで、被害者が警察への被害届や刑事告訴を取り下げるのが一般的な流れです。
示談の成立は、刑事事件の加害者にとって有利な処分をもたらす可能性があります。
刑事事件における示談の効果は、以下のケースがあります。- 被害申告の取り下げによって事件の捜査が終結する
- 証拠隠滅や逃亡の恐れがないと判断され、逮捕・勾留から釈放される
- 被害者の処罰意思が解消されたことを理由に不起訴となる
- 謝罪・賠償が尽くされていることが評価されて、刑罰が軽い方向へと傾く
2、示談がまとまらなかった! 交渉が失敗したときにおきること
刑事事件の被害者のなかには、加害者に対する強い怒りの感情などからかたくなに示談交渉を拒む人もいます。また、お互いが条件を譲らず交渉が難航してしまい、不和に終わってしまうケースも決してめずらしくはありません。
もし、示談交渉に失敗して話がまとまらなかった場合は、以下のような展開へと進む危険があるので注意が必要です。
-
(1)被害届が取り下げられない
被害届には、被害者の「被害に遭ったので捜査してほしい」「犯人を罰してほしい」という意向が込められています。
しかし、刑事事件の示談の和解条件には「被害届の取り下げ」を盛り込むことが多いため、示談が成立すれば、被害届が取り下げられ、被害者も刑事処罰を望んでいないものとして、不起訴となる可能性が高くなります。
一方、示談が不成立となり、被害届の取り下げが実現しなければ、逆に被害者が刑事処罰を望んでいるものとして、検察官も起訴する方向に判断が傾きます。 -
(2)検察官が起訴に踏み切る可能性が高まる
刑事事件として捜査が進展し、証拠がそろったうえで検察官が「厳しく罰するべき」と判断した場合は「起訴」される危険が高まります。
起訴とは、検察官が裁判所に対して刑事裁判を提起することです。検察官には、罪を犯したと疑われている被疑者を起訴するか、それとも不起訴とするのかの権限が委ねられています。
令和2年版の犯罪白書によると、令和元年中の刑法犯に対する起訴率は38.2%でした。
つまり、6割以上の事件が不起訴となり、刑事裁判が開かれないまま事件が終結しているという実情があります。
検察官が不起訴とする事情のなかには「被害者との示談が成立しているのか」という点も含まれているため、起訴を回避するには示談成立がきわめて重要です。
事件そのものの軽重にもよりますが、被害者との示談が成立しない事件では、検察官が起訴に踏み切る可能性が高いと考えておきましょう。 -
(3)裁判官が厳しい量刑を言い渡す可能性が高まる
刑事事件における示談は、裁判外で加害者と被害者が話し合って事件を解決する手続きです。
被害者に対して慰謝料などを含めた示談金を支払って許しを請う流れなので、本来は民事的な性格をもつものだといえます。
刑事裁判では、裁判官が証拠を審理したうえで有罪・無罪を判断し、有罪の場合は判決として法律が定める範囲で、具体的な刑事処分(量刑)が言い渡されます。
たとえば、傷害罪の法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金ですが、実際に言い渡される量刑は1か月~15年の懲役、あるいは1~50万円の罰金であり、どの程度の刑罰が言い渡されるのかはさまざまな要素が考慮されるのです。
示談が成立している場合は「民事的な賠償が尽くされている」と評価され、たとえ有罪と判断されても量刑が軽い方向へと判断が傾く可能性が高まります。反対に、示談が成立していなければ「被害者への賠償が尽くされていない」という評価となり、厳しい量刑判断を受ける可能性も高まることになるでしょう。
3、示談が成立したのに起訴されるケースとは?
刑事事件を穏便に解決する方策として示談はきわめて重要です。ただし、示談が成立したからといって必ず起訴を避けられるともいえません。
示談が成立したのに検察官が起訴を断行することもあるのです。
-
(1)「示談成立=不起訴」ではない
示談はあくまでも当事者間の和解であり、示談が成立したからといって罪を犯した事実が消滅するわけではありません。検察官が「厳しく罰するべき」と判断すれば、たとえ示談が成立していても起訴に踏み切られてしまうおそれがあります。
-
(2)示談が成立したのに起訴されてしまうケース
加害者・被害者の間で示談が成立していても、次のようなケースでは検察官が起訴に踏み切る危険があります。
- 厳しい刑罰が予定されている重罪である
- 実際に生じた被害の程度と示談金が釣り合わない
- 賠償は尽くされているが、被害者が被害届・刑事告訴の取り下げを拒否した
- 社会的に強い非難を受ける内容の事件である
- 過去の前科・前歴などから、加害者に反省の意思がないことが明らかである など
-
(3)「親告罪」と示談の関係
示談が成立したからといって必ず起訴を回避できるわけではないのが原則ですが“親告罪”にあたる事件では扱いが変わります。
親告罪とは、検察官が起訴する際の要件として被害者の告訴が求められる犯罪です。
たとえば名誉毀損(きそん)罪のように、事件化して公開の法廷で審理されたときに多くの傍聴人が被害者の不名誉な情報を得てしまうような犯罪では、被害者の告訴がないと起訴できないという定めがあります。
親告罪にあたる事件では、示談が成立して刑事告訴(被害届)が取り下げられると、要件に該当しなくなるので検察官は起訴できません。言い換えると、親告罪にあたらない罪では、示談が成立していることだけをもって不起訴が約束されるわけでないといえます。
4、不起訴につなげる示談交渉とは?
検察官が起訴に踏み切らない限り刑事裁判が開かれないので、不起訴となれば罪に問われないことになります。
できるだけ有利な処分を得るために、示談交渉において注目すべきポイントを整理しておきましょう。
-
(1)被害の回復がなされている
被害の回復は示談交渉の柱となる項目です。怪我の治療費、盗んだ物の返還・弁償、だまし取った金銭に相当する弁済、精神的苦痛に対する慰謝料などの賠償が尽くされることで「被害が回復した」といえます。
被害者の損害が今もなお存在しているのかを判断する材料となるので、被害の回復がなされているのかどうかはきわめて重要です。 -
(2)被害者が宥恕(ゆうじょ)の意思を示している
たとえ被害の回復がなされていても、被害者のなかには「お金の問題ではない、厳しく罰してほしい」と望む者が少なからず存在します。
示談成立の際に、被害者が「加害者を許す」という意思を示すことを“宥恕(ゆうじょ)”といいますが、宥恕の意思が示されていないと「犯人の処罰を望んでいる」という意向は打ち消されません。 -
(3)被害届の取り下げが約束されている
たとえ示談が成立していても、被害者が被害届を取り下げる手続きを取らなければ、事件の捜査や所定の刑事手続きは進行してしまいます。
示談の条件のなかで、被害届の取り下げが約束されていることを確認しなければ、せっかく示談金を支払っても期待したような効果は発揮されないおそれがあります。
不起訴を期待するなら、被害届の取り下げが約束されているのか必ず確認しましょう。 -
(4)合意内容が書面化されている
示談交渉において双方が合意した内容は、必ず書面化しなければなりません。口頭でも示談は有効ですが、どのような内容で合意したのかの証拠が存在しないと後々になって紛争の原因になってしまいます。
示談の合意内容は「示談書」というかたちで書面化するのが一般的です。ただし、示談書には合意内容を漏れなく記載する必要があります。
とくに、宥恕の意思や被害申告を取り消す旨の約束、示談以後の賠償請求はしないといった清算条項の記載は欠かせないので、個人による作成は望ましくありません。
効果的な示談は、交渉から示談書の作成まで、すべて刑事事件における示談交渉の経験が豊富な弁護士にまかせることをおすすめします。
5、まとめ
刑事事件における示談とは、事件の加害者と被害者が裁判外で話し合って和解する手続きです。示談が成立すれば、被害届が取り消されて不起訴となる、刑事裁判において有利な事情となり刑罰が軽い方向へと判断が傾くといった可能性が生じます。
一方で、示談成立は不起訴などの有利な処分を約束するものではありません。単に「示談が成立した」というだけでは不起訴になることが保証されるわけではないので、不起訴の可能性を高めるには効果的な示談交渉が必要です。
刑事事件における効果的な示談交渉は、数多くの解決実績をもつベリーベスト法律事務所 甲府オフィスにお任せください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています